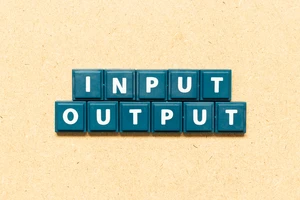ダイエットや栄養補給のために取り入れている健康食品やサプリメント。
ところが、それらが原因で健康を損なってしまう可能性が。
特に注意したいのが、肝臓への負担。
そこで今回は、肝臓がどのように働いているのか、なぜサプリメントが肝臓にダメージを与える場合があるのか、そして安全に摂取するための正しい飲み方について、解説します。
大切な肝臓を守りつつ、健康的な生活を送るために、ぜひ最後までご覧ください。


肝臓の働きとは?
肝臓は、体を元気に動かすための“重要拠点”とも言える臓器で、私たちの健康を支えています。
代謝
食事から摂った栄養(炭水化物・タンパク質・脂質)をエネルギーや体を作る材料に変えたり、糖分をグリコーゲンとして蓄えることで、血糖値を安定させます。また、体内に入った薬やアルコール、化学物質などを分解・処理して、無害化して体外に出しやすくする役割があります。
解毒
食品添加物や体内で発生した毒素、アルコールなどを分解して、体に害を与えない状態にしてくれます。これがうまく働いていると、体全体が元気でいられます。
胆汁の生成
肝臓が作る「胆汁」は、脂肪を消化しやすくするための液体です。脂っこい料理を食べたときにも、消化を助けてくれます。
栄養・ビタミンの貯蔵
肝臓は、糖質(グリコーゲン)だけでなく、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)、鉄分などのミネラルも蓄えて、必要に応じて、全身に供給してくれます。

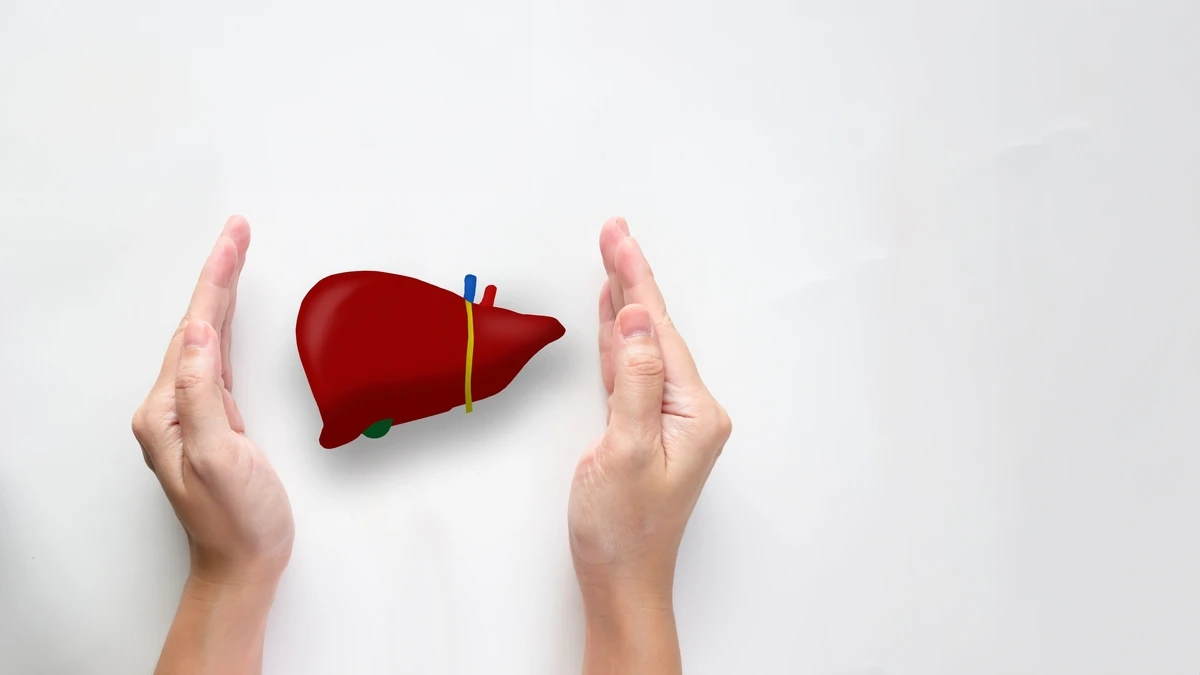
肝臓はなぜ「沈黙の臓器」?
肝臓は、一部が損傷しても痛みなどの明確なサインを出さず、静かに働き続ける「沈黙の臓器」として知られています。
肝臓には痛みを感じる神経が少ない
肝臓自体には、痛みを感知する神経がほとんどありません。そのため、多少炎症やダメージがあっても「痛い」「違和感がある」という信号が脳に届きにくいのです。
機能が低下しても代償できる
肝臓は再生能力が高く、機能がある程度失われても、残りの健康な部分でカバーしようとします。そのため、症状が出るほど機能が落ちるまで時間がかかり、表立った不調を感じにくくなります。
日常生活では気づきにくい
疲れやすい、身体がだるいなどの症状は他の原因でも起こりうるため、症状が肝臓の問題だと確信しづらく、病院に行くタイミングを逃してしまうことがあります。
このように、かなり進行するまで自覚症状がないため、発見が遅れやすいという特徴があります。
痛みやだるさ、黄疸(おうだん)などの目に見える症状が表れたときには、すでに重症化している可能性も少なくありません。


サプリメントの摂りすぎはNG
サプリメントを過剰に摂取すると、肝臓に大きな負担がかかり、肝障害を引き起こしたりとダメージのリスクが高まります。
負担が大きくなる
肝臓は、体内に入った栄養素や薬、化学物質などを分解・処理する“解毒工場”のような役割を果たします。サプリメントも例外ではなく、過剰に摂取した栄養素や添加物を肝臓が頑張って代謝しようとするため、肝細胞に大きな負担がかかります。
過剰摂取による毒性や相互作用
いくら体に良い栄養成分でも、大量に摂取すれば毒性が出る可能性があります。
例えば、脂溶性ビタミン(A, D, E, K)は、 過剰に摂取すると体内に蓄積されやすく、肝障害を引き起こすリスクが高まります。また、鉄や銅などのミネラルの過剰摂取で肝臓に沈着し、肝機能障害をもたらすことがあります。
添加物や不純物の影響
サプリメントには、カプセル素材や増量剤、香料などの添加物が含まれていることがあります。品質の低い製品や、海外製品の中には、不純物や重金属が混入している場合もあり、それらを肝臓が処理しきれずダメージに繋がることがあります。


こわい薬物性肝障害とは?
さらに、肝臓がダメージを受け、炎症や機能低下を起こしてしまう「薬剤性肝障害」という病気になる可能性もあります。
原因
病院で処方される医薬品、ドラッグストアなどで購入できる市販薬、場合によってはサプリメントやハーブ製品までもが原因になることがあります。
メカニズム
肝臓は体内に入った物質を分解・解毒する「解毒工場」の役割を担いますが、薬によってはその分解・代謝過程で有害な物質が生じたり、肝細胞自体を傷つけたりすることがあります。
主な症状
初期は、倦怠感(だるさ)、食欲不振、悪心(吐き気)など、風邪や疲労と見分けにくい症状が、進行すると、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、かゆみ、肝臓の炎症による腹痛や発熱などの症状がでます。
発症リスクを高める要因
複数の薬やサプリメントの併用、アルコールの過剰摂取、持病や加齢による肝機能低下、さらに薬の長期・大量使用などが挙げられ、これらが重なるほど肝臓への負担が大きくなり、ダメージが進行しやすくなります。
では、肝臓への負担を減らすには、どのようなことを意識して摂取したらよいのでしょうか?


健康の基本は「食事」から
日頃の食事が健康の基盤となるため、まずは食事からしっかり栄養を摂取することが大切です。
そのうえで、どうしても補えない栄養素がある場合や、特定の目的(妊娠や慢性疾患など)のために補助が必要な場合にのみ、足りない分のみを補うようにしましょう。
サプリメントはあくまで補助です。
偏った食習慣にサプリメントをプラスしても、根本的な栄養バランスの改善にはならないです。


用量をきちんと守る
サプリメントのパッケージや説明書に記載の「1日の摂取目安量」を守りましょう。
体に良い成分でも、摂りすぎると肝臓が処理しきれず、過剰症や肝機能低下を招くリスクがあります。


複数のサプリメントを同時に飲むときは注意
成分が重複する場合、過剰摂取になりやすいです。
例えば、鉄分やビタミンAなどは過剰摂取による肝臓障害を起こす可能性があります。


質の良いサプリメントを選ぶ
信頼できるメーカーやブランド
第三者機関の認証や試験を受けた製品を選ぶと、安全性が比較的高いと言えます。
海外製品などで成分表記が曖昧なものや、過度に「効き目」をうたう広告は要注意です。
添加物や不純物に気を配る
過剰な添加物や重金属が含まれると、肝臓への負担が増えることがあります。「無添加」や「オーガニック」といったキーワードだけでなく、原材料や製法もしっかりチェックすると安心です。


服用のタイミングに注意する
朝・食後・寝る前など適した時間を確認
脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は、食後に少量の脂質と一緒に摂ると吸収が高まります。
胃腸への負担を減らす
空腹時に刺激の強いサプリメントを飲むと、胃腸や肝臓への負担が大きくなる場合があります。
食事と一緒に飲むか、もしくは軽い間食をはさんでから飲むなど調整しましょう。


アルコールとの併用に注意
アルコールの代謝も肝臓が担っているため、飲酒しながらサプリメントを大量に摂取すると肝臓への負担が大きくなります。
特にビタミンAやナイアシンの大量摂取は、アルコールとの相互作用で肝障害を起こしやすいので要注意。
飲酒の時はタイミングをずらす
アルコールを摂取する際はサプリを避け、可能であれば別のタイミングで摂りましょう。


定期的な健康診断や血液検査
「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓は、トラブルがあっても自覚症状に気づきにくいです。
定期的に血液検査(肝機能検査)を受け、肝臓の状態をチェックすると安心です。
異常を感じたらすぐに相談
倦怠感、黄疸、尿の色が濃い、腹部の痛みなど気になる症状があれば、医師に相談してサプリメントの中止や検査を行うことを検討しましょう。


医師や薬剤師への相談を忘れずに
持病のために処方薬を飲んでいる場合、サプリメントの成分が薬の効果や副作用に影響を与える可能性があります。
自己判断でサプリを追加する前に、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。


さいごに
これらのポイントを押さえることで、サプリメントを安全かつ効果的に活用し、肝臓への負担を抑えながら健康を守ることができます。
飲み方に少しでも悩んだら、薬剤師や医師に相談するよう心がけましょう。