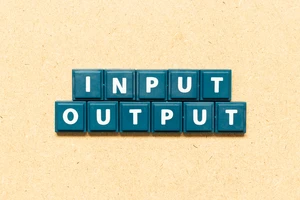夜勤やシフト勤務で「最近、体調がすぐれない」「よく眠れない」と感じていませんか?
実は、不規則な生活リズムは睡眠不足だけでなく、ストレスや体調不良を引き起こし、最悪の場合、事故のリスクを高めることもあります。
ですが、生活習慣を改めることで、睡眠の質を向上させることができます。
今回は、忙しい日々でも実践できる、体と心を守る快眠のコツをお伝えします。


シフト勤務が体に及ぼす影響とは?
シフト勤務や夜勤をすると、体内リズムが乱れ、体や心に負担がかかりやすくなります。
昼夜逆転による体の混乱
体は「朝に起きて夜に眠る」リズムで動いていますが、夜勤やシフト勤務ではこれが逆転します。夜に働いて昼に寝る生活が続くと、体が「今が昼なのか夜なのか」わからなくなり、不調を感じやすくなります。
集中力がさがる
日中に寝ようとしても、光や音の刺激でぐっすり眠れないことが多いです。これが原因で疲れが取れず、いつもだるいと感じたり、集中力が低下します。
胃腸の調子が悪くなる
夜勤中に食事を取ると、体が「本来は消化を休める時間帯」に働かされるため、胃もたれや便秘が起きやすくなります。
ストレスが増える
睡眠不足が続くと、気分が落ち込みやすくなったり、イライラが増えたりします。これが長期間続くと、心の健康にも影響を与えやすくなります。
健康リスクの増加
免疫力が下がるため、風邪をひきやすくなったり、感染症にかかりやすくなります。また、長期間の不規則な生活は、生活習慣病(高血圧や糖尿病)のリスクを高めることもわかっています。


睡眠障害の影響を受けやすい職業
以下のような不規則な勤務時間やストレスが多い職業は、睡眠障害に悩むリスクが高まります。
医師・看護師・介護士
夜勤や不規則な勤務スケジュールが原因で、体内時計が乱れやすいです。また、長時間の立ち仕事やストレスも重なり、睡眠障害を引き起こしやすくなります。
工場勤務・製造業
一般的に深夜シフトや交代制勤務なので、昼夜逆転生活になりやすく、睡眠時間が確保しにくい環境です。
飲食店・ホステス業
夜遅くまでの勤務や不規則な生活リズムが原因で、睡眠時間が乱れやすいです。
教師・教育関係
生徒への指導や準備作業、保護者対応などのストレスが大きいです。また、持ち帰り業務により、睡眠時間が削られがちです。
マネージャー・リーダー職
チーム運営や責任の重圧で、仕事のことを考えすぎて睡眠に影響がでやすいです。
自営業・フリーランス
働く時間を自由に決められる一方で、過労や休息不足に陥りやすいです。また、仕事の不安定さや収入の変動が、ストレスとなり睡眠に影響がでやすいです。
育児と仕事を両立する女性
家事・育児と仕事の両立により、自分の睡眠時間を確保できなくなりやすいです。
デザイナー・作家
夜間に集中することが多いため、昼夜逆転しやすいです。
ITエンジニア・プログラマー
納期やプロジェクトのプレッシャーで、睡眠時間を削りがちです。
では、体と心を守りながら質の良い睡眠を確保するために、どのような対策を取りいれたらよいのでしょうか?


昼夜逆転でも体内時計を整える
日中に寝る場合は、部屋を暗くするために遮光カーテンやアイマスクを使用しましょう。
また、起床後はできるだけ明るい光を浴びて、体に「朝が来た」と認識させます。これにより、体内時計がリセットされやすくなります。


睡眠の質を重視する
深夜勤務の場合
勤務前に1~2時間の仮眠を取ることで、夜間の集中力を向上させます。
また勤務明けは、帰宅後すぐに寝ることで疲労回復を早めます。
交代制勤務の場合
可能であれば、徐々に寝る時間を1~2時間ずつずらして、体に負担をかけないように調整します。


快適な寝室環境を整える
遮光・遮音
遮光カーテンで日中でも部屋を完全に暗くし、耳栓などを活用して外部の騒音をカットします。
室温
室温は16~20℃、湿度は50~60%を保つと快適に眠れます。夏はエアコン、冬は加湿器を使用しましょう。
寝具
寝返りしやすいマットレスや体に合った枕を選び、リラックスできる寝心地を確保します。


睡眠を妨げない食事を
深夜勤務中は、消化に負担が少ない軽めのもの(サラダやスープ)を選びましょう。
また、寝る前は脂っこいものや重たい食事、カフェインは避けましょう。バナナやヨーグルトなどの軽食がおすすめです。


リラックスを取り入れる
就寝前の瞑想や深呼吸、ヨガなどで体をリラックスさせる習慣を作りましょう。また、アロマセラピー(ラベンダーなど)を活用すると入眠を促進してくれます。


お昼寝は短時間で!
休憩時間に短時間(15〜20分)の昼寝を取ることで集中力を回復します。
ただし、30分以上の昼寝は逆効果になるので気をつけましょう。


シャワーでなく浸かる
就寝前に40℃程度のお湯に浸かると、体温が下がるタイミングで眠気が訪れます。入浴が難しい場合、足湯だけでも効果があります。


専門家のサポートを受ける
長期的に睡眠に問題がある場合、なるべく早く医療機関を受診し専門医のアドバイスを受けることも大切です。


さいごに
シフト勤務や夜勤が続くと、体も心も疲れやすくなりますが、ちょっとした工夫を積み重ねるだけで、心身の負担を軽くし、健康を守ることができます。
無理なくできる習慣を取り入れて、少しずつ睡眠の質を高めていきましょう。
毎日の小さな努力が、健やかで元気な体を作る鍵になります♡

2025年01月16日のみんなのアンケート結果!
毎日の美肌習慣、どっちを優先する?
回答人数:2682人でした!