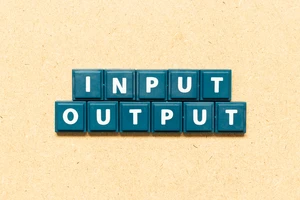「最近なんとなく足が痛いけど、きっと年のせいかな…」そんなふうに流してしまいがちな痛み。
もしかしたら、それ、“疲労骨折”のサインかもしれません。
今回は、“気づきにくい骨折”ともいわれる疲労骨折の予防とケアのヒントをお届けします。


疲労骨折ってなに?
疲労骨折とは、一度の大きな衝撃で起こる通常の骨折とは異なり、繰り返しかかる小さな負荷によって、骨に微細なヒビや亀裂が入る状態です。
骨が折れるほどの強い衝撃がなくても、日々の負担が蓄積することで起こりやすいです。
たとえば「長時間のウォーキングやランニング」「旅行や出張などでの急な運動量増加」など、頑張りすぎた日常の積み重ねで起こります。
よくある発症部位
✔ 足の甲(中足骨)
✔ すね(脛骨)

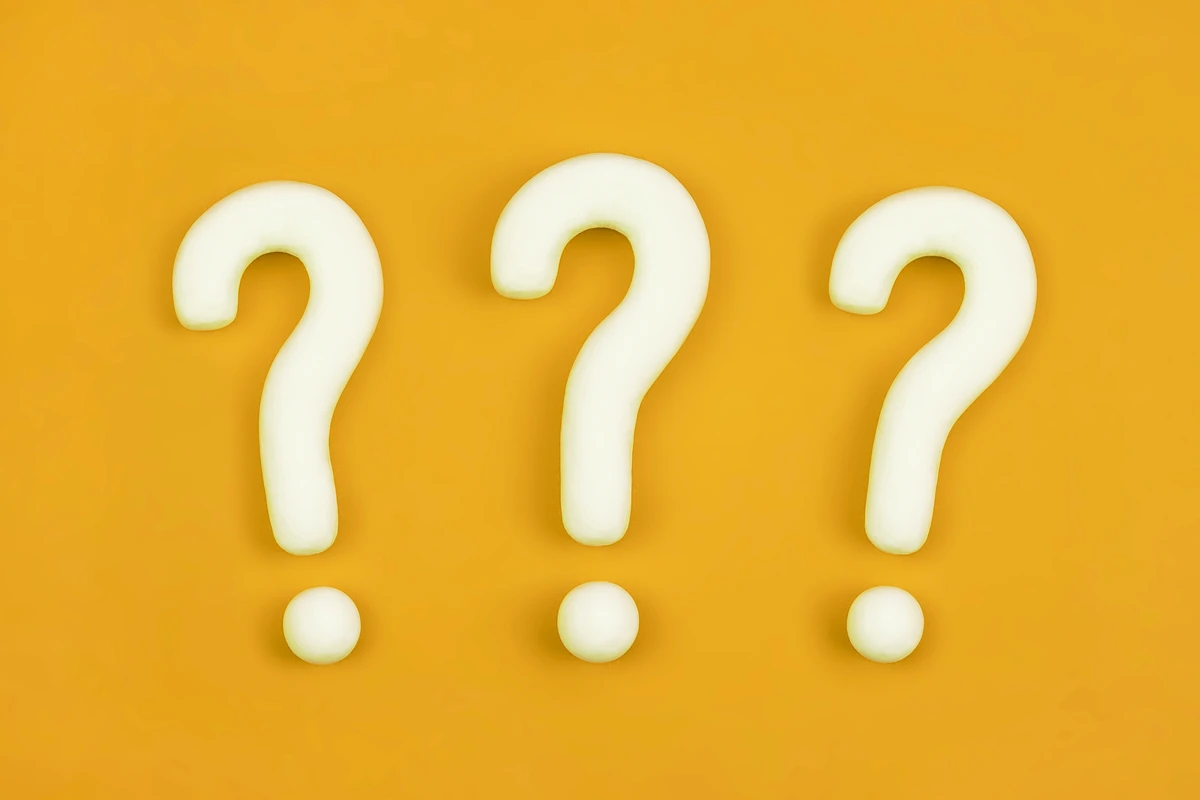
なぜ40代・50代に多いの?
ホルモンの影響
エストロゲンの減少で骨吸収が進み、骨密度が低下しやすくなります
筋肉量の低下
筋肉量が低下し、骨を守る“クッション”の役割ができなくなります
栄養不足
ダイエットや偏った食生活でカルシウム・たんぱく質・ビタミンDが不足ぎみです。
このような背景から、「急に運動を始めた」「体重が減った」「歩く機会が増えた」など、ちょっとした生活の変化が骨にとって大きな負担となることも。
とくに更年期前後の女性は要注意です。


疲労骨折の見逃しがちサイン
疲労骨折は、見た目には異常がないことがほとんど。
「隠れ骨折」とも言われ、初期はレントゲンで異常が見つからず、見逃されやすいのが厄介。
ですが、こんな症状があったら要注意です!
✔ 歩くと痛い・でも安静にしていると楽
✔ 骨の一部だけ「ピンポイントで押すと痛む」
✔ 腫れや熱感がある
✔ 骨に力をかけるとズキッとする


疲労骨折リスクをチェック!
以下のような方は、疲労骨折のリスクが高まります。
✔ 最近ダイエットや食事制限をしている
✔ 骨粗しょう症と診断された、または予備軍と言われた
✔ 急に運動を始めた
✔ ビタミンD・カルシウム不足を感じている
✔ 長時間歩く仕事・移動が多い・1日1万歩以上歩いている


放置NG!悪化すると?
疲労骨折を放置すると、以下のようなリスクが高まります。
✔ 完全骨折へ進行
✔ 骨の変形・機能低下
✔ 歩けなくなるほどの痛み
✔ 治癒に数ヶ月かかるケースも
特に、高齢者では寝たきりの原因にもなるため、早期発見と安静が大事です。


疲労骨折を防ぐ6つの習慣
「無理のない運動」からスタート
運動を始めるときは、いきなり長距離ウォーキングや高負荷トレーニングはNG。週に2〜3回、短時間から始めましょう。
クッション性のある靴を選ぶ
靴底がすり減っていたり、硬すぎる靴はNG。足にやさしい靴選びは、骨へのダメージ軽減に直結します。
筋肉をつけて骨を守る
筋トレは骨を支える“守りの鎧”。太もも・お尻・背中の筋肉を鍛えることで、骨の負担がぐっと減ります。
運動前後のケアを忘れずに
ストレッチ、アイシング、水分補給で“疲れを翌日に残さない”ことも大事です。
栄養で“骨の材料”を補給
カルシウムだけでなく、ビタミンD・ビタミンK・マグネシウム・タンパク質も意識的にとることが大切です。
紫外線不足に注意
ビタミンDの生成には、日光浴が不可欠。朝の光を浴びながらの散歩がおすすめです。


疲労骨折になったら?
痛みが続いているのに、「なんとなく放置」はNG。痛みがある間は、絶対に運動を控えましょう。
疲労骨折は、初期であれば自然治癒も可能ですが、進行すると完全骨折や変形治癒に至るリスクもあります。
早めに整形外科を受診しましょう。


さいごに
“なんとなくの痛み”にも、ちゃんと意味があります。
忙しさに流されず、自分の体の声にそっとやさしく耳を傾けてあげましょう。
それが、これからの10年、20年を健やかに歩むための第一歩です。

2025年10月22日のみんなのアンケート結果!
ホットフラッシュの対策は?
回答人数:62582人でした!